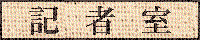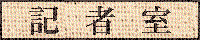-
漫画の危機
-
皆さんは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下【法】)」というのをご存じでしょうか?
大雑把に説明すると、読んで字のごとくなんですが、児童の権利を守るため、性的搾取及び性的虐待を防止するの法律です。
内容はこちらを参考してください。
元の文章は、慣れないとちょっと難しいので、簡単な日本語に直してあります。
より詳しく知りたい方は本文、又は概要を参考にしてください。
それもめんどくさいって人は、この法律は「18才未満のエッチなのはいけないと思います。」っていう法律だと思っていただければ大体あってます。
本当は順を追って説明したいくらいツッコミ所満載の法律なんですが、とりあえず掴みとして、身近な所から話しを始めたいと思います。
現在適用されているこの法律、改定される動きがあります。
どんな風に改定されようとしているかというと、絵も対象になる可能性が高いんです。
具体的にどうなるかというと、「18才未満が服を全部着てなかったり、一部を着てない状態(見てエッチだと感じられるもの)」は駄目って禁止事項があるんですが、これが絵にも適用される。
すると・・・お風呂&着替えシーン=NG(当然)、パンチラ=NG(ズボンはけ)、胸元or太股あらわ=NG(ちゃんと着れ)って話になりますな。18才以下のキャラに限りますが。
するってーと、ドラえもん&トトロ(入浴シーンNG)、サザエさん(パンチラNG)も駄目ですな。
胸元、太股関係は数えるのが嫌になるほど。
基本的に男女問わず適用ですから、男女でこれらのシーンが無い作品なんて、探す方が難しいでしょう。
それらのシーンが必然性有る無しに関わらず、作品を作る側からいえば、こんなこと規制されたら仕事にならん。ってのが正直なとこだと思います。
これが適用にでもなろうものなら、漫画に限らず、どのメディアも衰退は必至です。
もうちっとつっこんだ話まですると、「じゃぁ、どういう基準で規制するか?」って話になりますな。
考えられるのは、この二つ
1.設定年齢で判断
2.見かけで判断
1の場合、「実はこの作品の世界は異世界で、人間は超長命。この人も子供に見えますが実は10万8才なんです。」って言えば何でもOKか?って問題が出ますし、2の場合だと、「幼児体型ですが20才です。20才の幼児体型がいたら駄目なんですか?それは実際に幼児体型の人に対する差別なのでは?」と開き直ったらどうか?って話も出てきますな。
もっと極端な話をすれば、
W
x
Y
15才です、うっふーん。
これだけでも規制の範囲内ですな。
ついでに言えば、インターネットで広く「頒布」しているので、【法】第7条に基づき、3年以下の懲役又は300万以下の罰金です。
おかしいでしょ?どう考えても。
さらにはこの【法】の趣旨からすると、絵を規制の対象にすること自体、問題なのよ。
次回は「絵を規制する意義」のお話です。
続くわよ。
目次へ
部屋の最後へ
-
絵を規制する意義
-
さて、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下【法】)」の、児童買春を及び類似行為を取り締まるってこと自体は多くの人が賛成できることかと思います。(ホントはコレにも問題が→後述)
なにせ、実際に被害者がいるのですから。
では、実際に被害者がいない絵(漫画)に規制をかける意義は?というお話。
被害者も何も、写真だろうが絵だろうが児童ポルノは児童ポルノでしょ?
と、言い出すとこの法律自体の意味が無くなる。(もとから無いという話もある)
そんな事いったら児童ポルノだってポルノなんだから、刑法第175条わいせつ物頒布等の罪で処罰すればいいだけの話。
ついでに言えば、児童買春だって、「売らせる事」については売春防止法でほとんど処罰できる。
でも買春した場合の罰則規定が無い。
売春防止法の3条で「売っても買っても駄目」といいながら、自分自身で売った場合と買った場合の罰則が無いのは、ある程度、必要悪として認めている部分があるのかもしれない。(個人売買はOKということ)
これは児童が売春することについても同様。
これも児童の権利の一部なのか?
ただし、買ったら買春した人だけ罰則。
つまり個人売買でいえば(児童は)売春はいくらしてもいいが、誰も買っちゃ駄目。
変じゃろ?。商売としても成り立っていないし。
閑話休題
逆説的に考えると、次のことが科学的、統計的に証明されれば、この【法】で絵(漫画)も規制する必然性がある。
1.絵(漫画)により、児童の権利が侵害されている。
2.絵(漫画)により、児童買春等が助長されている。
1については、たとえロリ漫画であっても、モデルが特定できる場合を除き、登場人物は架空のものであるから、児童の権利が侵害されているとは言えない。
2については、エロ本があるから性欲があるんだ的な話。本末転倒。
ただ、ロリ漫画や変態性を伴うジャンルについては、メディア→実行ということが無いとはいえない。
その場合については、明確な分析と統計による証明が必要。
たとえば、児童を対象とした性犯罪者がいたとする。
だからロリコンは悪であるというのは単純すぎる。
その犯罪者はロリ系のエロ本を持っていたから、それが原因だ。
外のジャンルは持っていなかったのか?
その犯罪者の根本的な性的嗜好はどうなのか?
簡易な相手(抵抗されずらい)として狙った可能性もあるのでは
という、当たり前の観点が根本的に欠落している。
家に超兄貴があるからといってホモとは限らないのと同じだ(変なたとえ)
これらをクリアしないかぎり、この【法】で絵(漫画)を規制する必然性が無い。
この【法】の根本的な部分、そもそも児童と性の関係は?というあたりを、次回はやってみようかと思います。
・・・・・・だんだんディープな話になってくるな・・・。
目次へ
部屋の最後へ
-
寝言は寝て言え
-
と、ディープな方に脱線する前に、この法案、誰が言い出してどうしようとしてるのか?ってのを紹介しようと思います。
毎日インタラクティブというネットニュースの記事を紹介します。(http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200105/17/5.html)
言い出したのは「森山真弓 法相」(比例代表北関東ブロック選出 [自由民主党所属])
昭和2年の11月7日生まれとのことですから、74歳ですね(2月現在)
で、このばっちゃん、この法をこれからどうしたいかというと
1.児童ポルノの単純所持も禁止したい。
2.漫画、コンピューターグラフィックなどの「絵」も規制したい。
とのこと。
2については先に触れてるので、今回は1についてのお話。
現在、単純所持が禁止されてる物と言えば大きな所で銃と麻薬。
つまり森山ばっちゃんの頭の中では
18歳以下の裸の写真=銃や麻薬と同じくらい危険なもの(悪い物)
すごいですな。
写真でそれくらい危ないなら、実物はICBMくらいに危ないかも?
寝言は寝て言え。
現行法+単純所持禁止って案がもし通ったとしたらどうなるか?
某新聞は毎年写真コンテストをしてるんですが、たまーに夏の風景として、子供が裸(もしくはパンツ一丁)で水浴びをしてるような写真が出典され、賞をとって新聞に掲載されます。
現行法で行けばそれは児童ポルノでしょうから、単純所持禁止と併せて「発行部数×1世帯あたりの家族数」が法律違反で犯罪者になります。
これに「絵も禁止」を追加すると・・・
ちょっとまえの週間少年ジャンプ内の作品「ONE PIECE」で、18歳以下の入浴シーンがありました。
(絵が禁止なら)当然児童ポルノです。
ってことは「ジャンプの発行部数350万部×1世帯あたりの家族数」が同様に犯罪者になりますな。
最低350万人、1世帯3人としても1000万人以上が犯罪者。
ま、これはネタですけどね。(真面目にツッコミ入れないでね)
先の毎日インタラクティブの記事にもありますが、いくら何でも単純所持禁止と絵禁止は問題あるだろうってんで、現行法では対象になりませんでしたが、森山のばっちゃん、11月の改正時に入れる気満々です。
この辺りを
・最初駄目だったんだから今回も(絵や単純所持禁止が規制されず)大丈夫だろ
と、考えるか、
・今度こそ無理矢理にでも(絵や単純所持禁止を)通すだろ
と、考えるかは微妙なところですが、警戒しておくに越したことはないかと思います。
目次へ
部屋の最後へ
-
危機感を煽ってみる
-
前回、「なんとかなるかも?」くらいの引きだったので、今回はちょっと危機感を煽ってみましょう。
この「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下【法】)」が施行されたときに、、紀伊国屋が各支店に送ったファクスの内容をご紹介しましょう。
紀伊国屋FAX:
(http://web.archive.org/web/20000302035724/www.din.or.jp/~kamayan/kinokuniya.htm)
読むのが面倒な方は、紀伊国屋本店から支店への「自主規制要望FAX」だと思っていただければ、大体あってます。
この法が施行された時点では「絵」は規制の対象になっていません。
ですので、一部、的外れな対応部分もありますが、逆にいえば今回の改定で「もしも」「絵」が対象になった場合、間違いなく同じような、いや、これ以上の(自主規制を含む)規制がかかることは間違いありません。
ちなみにこのFAXによって、店頭から姿を消した作品で有名所といえば
「バカボンド」(井上 雄彦/著・講談社/刊)
「ベルセルク」(三浦建太郎/著・白泉社/刊)
もう、馬鹿かと、阿呆かと。
「バカボンド」といえば「講談社漫画賞受賞作品」
「ベルセルク」だって「手塚治虫文化賞 第4回マンガ大賞 最終選考作品」ですよ?
二作品共に日本を代表する漫画として選ばれてもおかしくない作品です。
勘違いしてはいけないのが、こういう対応をしたからといって、紀伊国屋が悪いわけではありません。
企業として企業自体と社員を守るため、こういう対応は仕方なかったと思います。(多少勘違いはしてるが)
書店や企業などが、こういう対応を執らざるを得ない、この法に問題があるのでは?
と、いうことです。
自主規制の話をしましたので、こんどは「取り締まる側」からの判断を紹介しましょう。
基本的には「警察」の判断して取り締まり、「裁判所」で最終的な是非を問う事になるかと思います。
ですので、どういう判断をもって有罪とするか?という所が焦点になってくるでしょう。
裁判所は過去の判例を重視しますので、似たような判例がないか調べてみました。
ありましたよー。
「チャタレー夫人の恋人」事件判決(最高裁昭和32年3月13日判決<判例時報105号76頁など>)
刑法第175条(わいせつ物頒布等)に関する事件で、最高裁まで争われました。
焦点は「なにをもって【わいせつ】とするか?」
ここで最高裁判官達はこう公言しています。
「かりに一歩譲って相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても、裁判所は良識をそなえた健全な人間の観念である社会通念の規範に従って、社会を道徳的退廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。」
かみ砕いていうと
「世間がどう思おうと俺達(裁判官)が(わいせつかどうかを)決める。」
言い方を替えれば
「世間で(この作品を)わいせつだと思わなくても、私たち(裁判官)が、わいせつだと思ったら、それは、わいせつである。」
裁判官の主観で有罪にされたら、たまったもんじゃありません。
さて、危機感が出てきましたでしょうか?
ちなみにhttp://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/comp/int_c_obs.htmlを参考にさせていただきました。
他にも、「わいせつ物の定義」について興味深い話が載っていますので、興味のある方は一読されることをお勧めいたします。
目次へ
部屋の最後へ
|