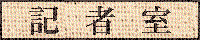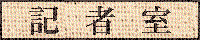-
著作権について(解答編)
-
さて、前回掲載した「著作権について(引用編)」について、先日掲示板の方に、このような書き込みをいただきました。
引用について
とりあえず、気になったので、書き込みます
>「ゴー宣」著作権問題の判決について
>著作権法32条
>「公表された著作物は、引用して利用することができる。
>この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」
>
>にいう「公正な慣行」「正当な範囲」とは、次のような条件で、これらを守っていれば、著作権者の許諾なく引用することができる。
>
>論評の場合は、
>
>1.論評が「主」、引用が「従」である。
>2.論評自体が独自の創作である。
>3.論評と引用部分が明確に区別できる。
>4.引用部分の出典を明記する。
>5.引用する必然性がある。
>6.引用の結果が出典の意図を損なっていない。
>7.引用は正確でなければならない。
>8.引用した著作物から、引用元の著作物全体を再構成できないようにする。
>(俳句や短歌などは例外)
>
>「学術研究」「報道」などにも同様のルールが適用される。
>
>参考URL
>http://www.bunka.go.jp/8/VIII.html
>
>上の条件に合致しない著作物の利用は、「転載」と呼び、著作権者の許諾が必要になる。
>許諾なく転載するのを「無断転載」と呼び、違法行為になる。
>
>漫画で歌詞を利用するときに、欄外などにJASRACの許諾文が載っているのは、これが上の条件を満たさない(論評や研究、報道などではなく、物語の1シーンに利用しているだけである)ため。
>
>模写は、やはり上の条件を満たしていないなら「複製」になる。従って、許諾なく模写した場合は「無断複製」に当たり、「無断転載」と同様の違法行為になる。
引用の条件は上記のように厳密です。
もちろん、無法地帯記者室に書いてあるような場合は認められません。
おせっかいかと思いますが、訂正なされたほうがよいかとぞんじます。
読みやすい用に改行等を加えた他は原文ママ
また、一応、お名前は伏せさせていただきました。
|
まったくもって、おっしゃる通りです。
先に「著作権について(引用編)」で書いたような事が、まかり通って良いはずはありません。
前回の文章は判決を極論で書き、それを皮肉(というより揶揄)ることにより、問題提起することを目的とする文章なので、訂正こそしませんが、本来、引用とは、かくあるべきものです。
では、前回の「新・ゴーマニズム宣言」の問題については、どうか?というと、今ではこれについては、そのうち出るであろう単行本を買うなり立ち読みするなりして、人それぞれの判断を得たいところですが、私個人としては上記の条件を満たしているとは思えません。
法律というのは、解釈の仕方で結論が反転するのは珍しく無いですからね。
逆転勝訴とか逆転敗訴とかもありますし。
あくまで、(正否は別として)私はそう解釈しました。
皆さんはどう思われますか?
Yahoo掲示板などで、意見が交換されていますので、興味のある方は行かれてみては?
それとは別に、今回がそう、というわけでは無いですが、少なからず法律に携わる仕事をしている者の経験から言うと、「法律は往々にして歪められる」ものです。
周囲の状況や力関係、裁判の場合については、裁判官の心情、性格によってまで法の解釈が変わってきます。
一応、建前上、三権分立や前例を重視するなどの形をとってますが、沖縄の基地問題の裁判の時は、圧力がかかったのか、明らかに政府寄りの判決を出したりしますし、セクハラを含む性犯罪系の判決の時は、性別により判決の程度が違うなどという話は結構メジャーな話です。
これは人が人を裁く以上、ある程度は仕方が無いことなのかもしれませんが、少なくても法治国家として、(知的所有権関係は特に)個人の価値観や周囲の圧力などによって判決が変わることが無いようお願いしたいものです。
「歪められる法律」については、機会があれば、またお話したいと思います。
最後に引用についてご指摘をいただいた方につきましては、ネットでの指摘は(小林よしのり系の文章は特に)粗暴かつ感情的な物が多い中、理知的かつ丁寧なご指摘をいただきまして、感謝とともにお礼申し上げます。
目次へ
部屋の最後へ
-
著作権について(引用編)
-
さて、最近なにかとうるさい著作権についてですが、つい先日、面白い事例がでましたのでご紹介します。
ことの起こりは、「ゴーマニズム宣言」の著者、小林よしのり氏が、同作品のカット・コマなどを無断で引用したと「脱・ゴーマニズム宣言」の著者、上杉聰氏を訴えたのが始まり。
「脱・ゴーマニズム宣言」は「ゴーマニズム宣言」の内容について評論する内容。
それに伴い、「ゴーマニズム宣言」より多数のカット・コマを無断で引用していた。
結局、裁判では上杉氏が勝訴したのですが、その裁判内容について、小林氏が雑誌「SAPIO」で連載している「新・ゴーマニズム宣言」についていろいろかかれています。
詳しくは店頭で「SAPIO」10月13日号を見ていただいたほうが早いので、割愛しますが、おおざっぱに説明すると
無断で人の漫画使うな!
資料だよ資料。読者の評価に必要だろ?
っつーわけで、使ってもOK
と、いう話。
すごい話ですね。
上杉氏の「脱・ゴーマニズム宣言」は俗に言う「批判本」
「批判本」のためなら、相手の作品を無断に使ってもOKってんだから、ソレ系の作者はもとより、謎本や同人誌作家は大喜びですね。
極端な話、1本の漫画を無断でマルマル載せて、最後に「このような主人公の行動は青少年に悪影響を与える」とか書いておけば、それでOK。
あとは「批判に対する読者評価への資料として載せました。」って言っておけばお咎め無しってんだから、著作権もへったくれも、あったもんじゃないと思うのだが・・・
カットでも同様に、たとえば著作権にうるさい某会社のキャラクターのカットを無断で使っても、下に「ここのラインはおかしい」とか「この配色は変だ」とか書いておけば、「批判に対する読者評価への資料ですから。」で通る。
まあ、「読者評価への資料」ですから、かならずしも批判しなくてもカットの下に「○○萌え〜」とか書いておけば「そうおもうだろ?」という意見に対する「読者評価の資料」ってことで載せましたでOKだの。
結局、小林氏はこの判決を不服として、控訴したそうですが、どうなることやら・・・
皆さんはどう思われますか?
目次へ
部屋の最後へ
-
日の丸・君が代2
-
さて、前回の「記者室」で話題にした「国旗・国歌法案」についてですが、つい先日「強行採決」されました。
ま、簡単にいえば、政党同士(この場合、自民党、自由党、公明党。俗に言う「自自公」)が手を組んで、数(人数)で多数決を押し切った。と、いうところ。
さて、ここで不思議なのが、
「なぜ、強行採決までして法案を通したか?」
という点。
これが「大店法(大規模小売店法:大型店舗の出店を規制する法律)」の緩和とかいうのであれば、強行採決することにより、その見返りに大型店舗を出すような大企業から、便宜をはかった議員や政党に賄賂が・・・と、(良い悪いは別として)納得できるのだが、国旗・国歌法案をとおしたって、さほど金にはならないでしょうし、何よりこの不景気で経済の建て直しが第一課題である中、議論しなきゃならないほど、(国民にとって)大事な問題ではないはず。
つまり、「国旗・国歌法案の強硬採決」は、公益はもとより(議員・政党の)私益とはさほど関係のない理由によって行われた。と見るのが普通かなと思います。
では、どんな理由で?という話になるのですが、一番ありそうなのが
「やりたかったから」
馬鹿みたいな理由ですが、おそらく間違いないと思います。
では、誰が?という話になりますが、日本という国は、とかく「殿様」と「家来」という社会構造が好きならしく、「家来」は「殿様」に従うこと、反対や意見などもってのほか、それらを進言したとしても「殿様」はきかない。
「家来」は道理はともかく「殿様」のご機嫌をとることを第一とする。といった社会構造が今だ残っているようです。
簡単にいえば、社会人の皆さんであれば、「上司」と「部下」の関係を見ていただければ、だいたいわかると思いますが、馬鹿げた無茶な命令を出す「上司」が「殿様」。
それに無条件に従ってしまう、太鼓持ちのような「部下」が「家来」といった関係といえばわかりやすいでしょうか?
つまり、現議員もしくはそれ以上の権力を持つ者が「やりたかったから」下っ端の議員達が強行採決までして法案を通した。といったところだと思います。
日の丸と君が代が好きで、かつ、それだけの権力を持っている者、となると、そうゴロゴロいるわけもなく、皇室関係者か、先の戦争で良い目をみたorまだ悔しがっているタカ派の長老議員といったところが妥当な線でしょう。
ですので、「天皇陛下即位満10周年記念式典」にむけて、(ご機嫌とりに)「国旗・国歌法案」を通そうとしたのではないか?という「生臭い噂」も、馬鹿にできませんし、「日米ガイドライン(戦争や紛争など有事の際、アメリカ軍に日本の自衛隊も補給等の分野で協力するという協定)」などと一緒に考えると、「おえらいさん」の「戦争したい病」がまた始まったのかもしれません。
前者ならまだかわいいものですが、後者であればかなり問題ですね。
もし後者であれば、これから様々なメディアで(戦争に向けての)世論誘導が出てくるはずです。
政治に関心を持てとまではいいませんが、自分の身を守るためにも、少し警戒しなければならない時期に来ているのかもしれません。
さて、皆さんはどう思われますか?
目次へ
部屋の最後へ
-
日の丸・君が代
-
さて、初めからディープな、お題ですが、教科書の検定や、国旗・国歌の法制化など紙面を賑わしている、「国旗・国歌問題」について、今回は一言。
ご存じの通り、現在、「日の丸・君が代」を国旗・国歌として法制化しよう。また、教科書でも、「それらを尊重する態度を育てる」ように検定しています。
乱暴ないい方をすれば、それについて賛成派は「今まで使ってきたんだから、これでいいじゃん。」
反対派は「戦争とかの悪いイメージがあるから駄目じゃい。」と、表向きの理由はなっています。
まぁ、それぞれ更に裏があるのでしょうが、「無法地帯的」には、「日の丸はOKで、君が代は駄目」
理由としては、太陽をデザインした日の丸は、古来から、しかも1000年単位前から日の本の国として、日いずる国として名乗っていた慣習があり、たとえ途中悪いイメージの出来事があったとしても、それだけでは無かったはず。
当然、逆に日本の旗のもと、善行を行った人や団体もあるはずです。
善行も悪行もひっくるめて一つの国であるからには、いちいち悪いイメージがあるから駄目というのでは、何もできないでしょう。
そういう意味で、日の丸については、賛成派ですね。
では、君が代についてはどうかといいますと、国歌とするからには、当然、内容が日本に適したものではなければならない。
当たり前ですね。
では、君が代の歌詞の内容は、どんなのでしょう?解説を入れながら、ちょっと記述してみます。
- 君が代は
- 天皇陛下(君)が治める世の中は
- 千代に 八千代に
- 千年も、それ以上に長い年月ずっと([八]は、多いということを表現している)
- さざれ石の 巌をなりて
- 「さざれ石」は、風などによって、砂や小石が集まり、固まってできる石のこと、形成されるまで長い年月がかかるらしい。
それがどんどん集まって巌(大きな石)になるほどの時間・年月
- 苔のむすまで
- 苔が生えるまで(苔のはえるほど、長い年月)
まぁ、二番もあるらしいですが、ぶっちゃけた話
「天皇陛下、いつまでも僕らを治めてね。」
と、いう内容。
逆にいえば、日本なんてどうでもいい感じです。(国民含む)
君主制の国ならいざしらず、一応、民主主義の日本の国歌じゃぁないでしょう。これは。
と、いうわけで、君が代は国歌としては駄目。
さて、皆さんはどう思われますか?
追記:日本国憲法で「天皇は国民の象徴」とうたっているのだから、「国民主体の世の中がいつまでも続きますように」というふうに解釈できるんじゃない?という意見は考えすぎだと思います。
追記2:わざわざ法制化しなくても良いんじゃないか?とうのが本音です。
目次へ
部屋の最後へ
|