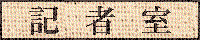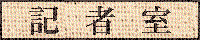-
選挙のお話
-
選挙の結果がでましたねぇ・・・
比例区と小選挙区での与野党の得票率が逆転しとりましたね。
小選挙区ってのは基本的に地域に利益を誘導できる議員とか堅い地盤がある議員に有利なんすよ。
中選挙区とかにくらべて小範囲の選挙区だから、一気に金も力もつぎ込めるし、当選は1名のみだから、議席取ってしまえば、逆に他の候補者は全員落ちるしね。
つまり、与党に有利な選挙区な訳。
なんせ、国家予算から公共事業とかで金ばらまく権利ある訳だしね。
嫌な特徴としては、「死票」が多い事。
1票でも多く獲得した人のみが当選なんで、たとえば5人が立候補していたとして、得票率がA氏が21%、B氏が19%、C氏〜E氏までがそれぞれ20%だったとすると、当選したA氏の21%の投票しか当選という形で民意が反映されない。
つまり、残りの79%の投票はまるっきりの無駄。
これが「死票」
極端な話、全選挙区が先ほどの例のようになると21%の投票で総ての議席をゲットできる。
ま、それはいくらなんでも、まずいだろうということで、日本では「小選挙区比例代表並立制」っていう制度をとってます。(なら、最初からやるなという話しもあるが・・・)
簡単にいえば、先ほどの小選挙区制で300人くらい、比例区制で200人くらい議員さんを選びましょ。という制度。
比例区制ってのは、政党別に投票してもらって、その得票率に応じてそれぞれの政党から当選人数を決定するという制度。
もちろん政党内ならだれでもいいというわけじゃなく、あらかじめそれぞれの政党で用意して登録してある名簿の上から順に当選するというカタチ。
特徴は総ての投票が「率」という形で当落にかかってくるので、「死票」が極めて少ないということ。
ある意味、民意がもっとも伝わりやすい制度。
弱点は投票が政党単位なので、少人数のため比例区制の対象とならない小政党や個人などは対象にならない事。
少数意見が反映されないって事やね。
この二つを組み合わせたのが「小選挙区比例代表並立制」という訳です。(本当はもっと複雑)
今回の場合、結局、結果的に与党側としては小選挙区での結果から「国民は与党を選んだ」と言い張るし、逆に野党側は比例区での結果から「与党は国民から信任されていない」と言い張る。
実際どっちかというと、後者だと思うんだけどね。私。
与党側は投票率が高くなれば高くなるほど不利になるというのは割と有名な話。
得票率が低いってことは、極端な話、一部の政治に関心のある人を除いて、利益とか絡んで熱心な、というか会社からとかの圧力で投票させられる人(与党派が多い)の比率が高い状態。
得票率が高くなればなるほど、そういう人たちの比率が低くなる。
利益がらみの意志が薄められて行くという事。
ゆえに与党側が不利になる。
というか、政策勝負ということで野党側と同じ土俵に立つだけなんだけどね。
ま、うち(無法地帯)の文章は極論で揶揄するという形なので、本気で総ての与党支持者が利益がらみだというつもりはないですが・・・
今回はこれだけ得票率が低い状態(与党側が有利)で、比例区の議席数を野党側に上回られたんだから、少なくても胸張って「国民から信任されている」といえるような状況じゃないと思うんだけど・・・
少なくても小選挙区は人を選び、比例区は政党を選ぶという大前提から、当選議員事態はともかく、与党は信任されていないと考えるのが普通かと思う。
みなさんはどう思われます?
目次へ
部屋の最後へ
|